焼き物にっぽん地図
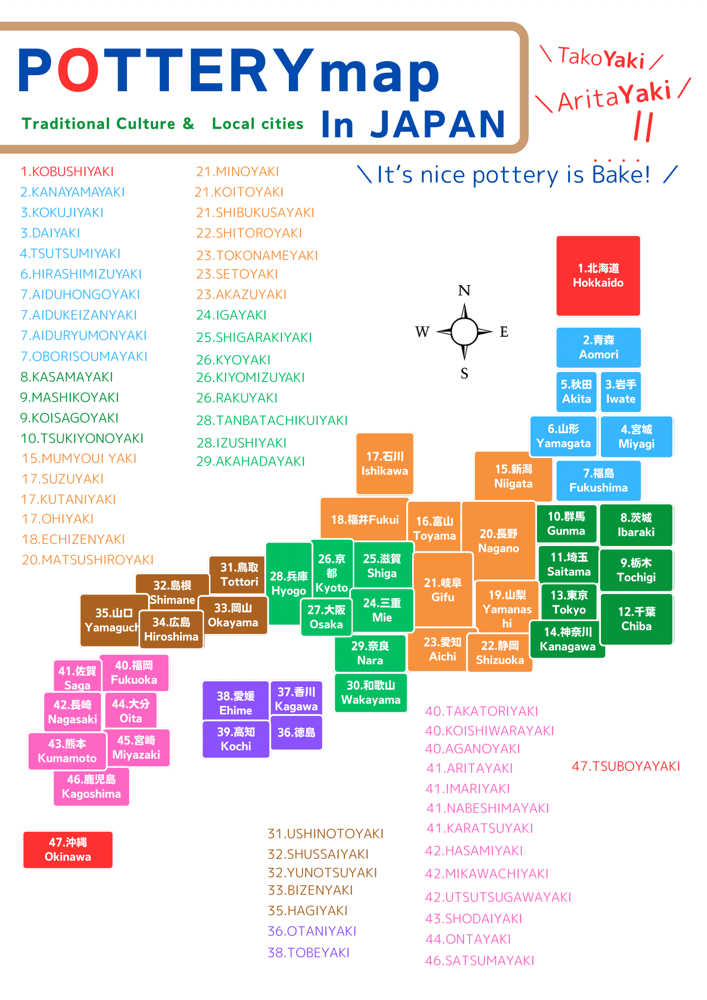
1. こぶ志焼(北海道)Kobushi yaki
戦後間も無く誕生したこぶ志窯。民藝運動が始まった頃北海道を代表する焼き物を目指そうと天目や辰砂釉など技術的にも高度な釉薬研究にも取り組まれている。玉虫釉・緑彩釉・白釉などどの色も美しく見応え抜群となっている。雪が多いことで知られる遠い岩見沢の地から生活に根ざした新しい焼き物を発信、現在3代目の千秋氏が現在も改良し続けている看板カラーの『海鼠釉』は、北海道の広大な空や海を連想させる料理の映える複雑な艶やかな青色で絶大な人気を博している。
2. 金山焼(青森県)Kanayama yaki
津軽金山の大溜池の底にたまった良質の粘土を使い薪窯で作られる。「新しいのに懐かしい」をコンセプトに、備前から学んだ窯業技術をもとに現在3基の大きな窯の中で多様なうつわが焼かれている。使い込むと艶が出るというその肌合いは、青森県を代表する焼物としてそのファンを増やし続けている。
3. 小久慈焼(岩手県)Kokuji yaki
1813年相馬の陶工より技術が伝わる。家系に代々技術を引き継ぎ江戸時代以前から現在まで1軒のみが作る北限の唯一無二の焼き物である。地元の粘土、独自の釉薬が作るのはわら灰ベースの白と砂鉄を使ったアメ釉の2種のみ。形もシンプルに考え抜かれており、久慈市内のどの家庭にも一つは所有されている程生活に根付いている。鉄分の少ない粘土から作られる白釉は温かみのあるクリーム色が一面に溶け明治期には民藝の父、柳宗悦氏にも評価された。
3. 台焼(宮城県)Dai yaki
4. 堤焼(宮城県)Tsutsumi yaki
6. 平清水焼(山形県)Hirashimizu yaki
江戸時代後期に陶工小野藤次平を茨城より招いて千歳山の鉄分のやや多い土を焼いて作った焼物である。土に含まれている鉄分が還元焼成で青い斑点となり(酸化焼成で鉄分は黒や赤になることが多い)、梨地のような肌合を作るのが特徴となっている。
青龍窯の作品はかつての万博で海外にも認められ平清水焼の名を世界に知らしめた。青みがかった肌にごま塩のように黒い斑点があるのがこの焼き物の独特な楽しさを作っている。
6. 上ノ畑焼(山形県)Kaminohata yaki
上の畑焼は日本最北端、最古の磁器の窯である。江戸末期に長瀞(ながとろ)藩が地元の陶石を使った作陶を産業にしようと、伊万里の流れを汲む陶工を大阪から招いて窯を開かせたが、財政難のため、わずか10年ほどで廃窯してしまった。この窯をよみがえらせたのは、上の畑焼の復興を決意して陶芸の修行を積んだ伊藤瓢堂(いとうひょうどう)。白地に藍色の文様が特徴の上の畑焼。伝統の絵付けの中でも代表的なものが、桃・柘榴(ざくろ)・仏手柑(ぶっしゅかん)を描いた三多紋(さんたもん)である。最近では金や赤を追加したり、銀山の銀を掘った廃鉱から出る鉄錆を用いた焼き物を製作するなど、現代の生活感覚に合ったさまざまな作品を作っている。
7. 会津本郷焼(福島県)Aidu hongo yaki
7. 会津慶山焼(福島県)Aidu keizan yaki
7. 会津流紋焼(福島県)Aidu ryumon yaki
8. 笠間焼(茨城県)Kasama yaki
江戸時代半ばに信楽の陶工を招いて始めて作られたもので、壺や鉢のような日常雑器を中心に発展してきた。現代では多くの若手の陶芸家たちがこの地に集まり、自由な発想の楽しい器も多く見られる産地になっている。隣接の益子とともに東京から近いという立地もあり、近年多くのファンを獲得している。関東ローム層から出土する蛙目粘土(がえろめねんど)と呼ばれるきめの細かな陶土が主な材料のため、焼き上がりの丈夫な器になっている。ただ近年の陶芸家たちは他産地の陶土を使って幅広く様々な作品に挑戦している人が多い。
毎年ゴールデンウィークに開催される陶炎祭は笠間周辺の多くの窯や作家が参加する楽しいイベントになっている。
9. 益子焼(栃木県)Mashiko yaki
江戸時代末期に大塚啓三郎が益子の地に窯を築いたのが始まりとされている。その後浜田庄司らの民芸運動とともに広く全国にその名が知られるようになった。浜田庄司に続いて島岡達三が人間国宝になり、益子焼は揺るぎない民陶の里になった。駅弁「峠の釜飯」の釜の産地としても有名で、民陶以前は奈良時代から、私たちの生活における必要具の甕やすり鉢など台所品を作っていた。
毎年ゴールデンウィークには近隣の窯も含めて500を越える窯が集まり盛大な陶器市が開催されている。
9. 小砂焼(栃木県)Koisago yaki
水戸藩の御用窯として庇護されてきた小砂焼。馬頭温泉の近くから産出される良質の陶土を使って、かつては茶器、今では生活雑器が焼かれている。「金結晶」と呼ばれる黄金色の釉薬や薄紅色の辰砂(しんしゃ)釉が特徴的で上品で華やかな味わいのある器である。田園地帯の一角に数軒からなる焼き物集落が形成されており、のんびりと焼き物見学をするには絶好の環境で作られている器である。
10. 月夜野焼(群馬県)Tsukiyono yaki
15. 無名異焼(新潟県)Mumyoui yaki
この不可思議な名前の焼き物は新潟県佐渡市産であります。
無名異(むみょうい)とは、佐渡金山のその坑中の石英岩から採れる、酸化鉄の赤血色をしたきめ細かい粘土をいいます。
この焼き物は高温で焼き締める為非常に硬く、時期の様な焼き上がりをしています。かつては血止めの霊薬として珍重される程で、無名異焼で飲むと美味しいお茶が飲めると、各国のお茶愛好家から熱視線を集めています。
スタッフも実感済み。お茶やコーヒーも美味しいですよ!
17. 珠洲焼(石川県)Suzu yaki
石川県珠洲市で焼かれる焼き締めの焼き物である珠洲焼の起源は、古墳時代の須恵器にさかのぼる。平安時代の終わりごろから鉄分の多い珠洲の土を使って焼かれた珠洲焼は、鎌倉時代に入り日本海側を中心に全国で広く使われるようになり中世の日本を代表する焼き物になったが、その後はすっかり姿を消し作られなくなってしまった。現代になり珠洲市が、珠洲焼を復興し若手の作家を中心に製作が盛んになってきた。黒く焼きしまった珠洲焼はぐい呑・ビールカップ・湯呑など現代人にも大変人気になっている。2024年能登半島地震や水害の被害を甚大に受けながらも、珠洲焼を作り続けるという選択をしてくださった作家方には尊敬の念が絶えず、変わらず手に取る事が叶い嬉しい限りである。
17. 九谷焼(石川県)Kutani yaki
江戸時代に大聖寺(だいしょうじ)藩九谷村で良質の陶石を使って焼かれたのが起源とされているが、当時のものは、言わば古九谷焼とは作調の違うもので、古九谷焼(古九谷様式ともいう)は有田の山辺田窯周辺で作られたものと近年思われるようになった。
九谷焼の特徴は緑・黄・青などの濃色を使って大胆な生き生きとした図柄が多いこと、また一方では明治期の九谷庄三に代表される精緻な赤絵の技法にあり、器一つに百人一首の短歌をすべて書き込むなど他産地にはない独特の絵付け文化を完成させている。
江戸時代日本海側が日本の表玄関だったころ、そして金沢が江戸・大阪に次いで我が国第三の都市だったころからの北陸の文化を代表する焼物である。石川県小松市寺井の九谷焼団地では人間国宝の徳田八十吉(やそきち)、吉田美統(みのり)の作品を見ることができ、宮内庁御用達で知られる藍古九谷(染付)山本長左の作品は数々の料理人・器好きを魅了してやまない。
18. 越前焼(福井県)Echizen yaki
釉薬を用いずに高温で焼き上げる器で、焼成時の薪の灰が器に降りかかり自然釉としてできた器の景色(器表面の風合い)を楽しめる焼き物である。歴史は古く平安時代にさかのぼる。かつては産地の織田村の名前をとって織田焼と呼ばれていたが、日本六古窯に指定された際に越前焼と呼ばれるようになった。かつて日本海側で大量に普及していた能登半島の珠洲焼にとって代わって、この越前焼は日本海側の広い範囲に普及していた。江戸時代他の産地が茶器を生産したのに対して、越前ではかたくなに生活雑器のみを作っており、お歯黒壺や種壺、水瓶などを中心に制作されていた。その為現代になり急激に衰退したが、現在再興の活動が盛んになっている。
20. 松代焼(長野県)Matsushiro yaki
21. 美濃焼(岐阜県)Mino yaki
桃山時代になり茶の湯で育み花開く。自由で生き生きとした焼き物が登場した。それまでの須恵器(すえき)ではなく釉薬をかけ絵付けをした我が国独自の文化ともいうべき器の誕生の裏には古田織部などの茶人の力が大きいと言われている。志野・織部・黄瀬戸などの我が国独自の陶器がこの時代に次々と生まれ「美濃桃山陶」と言われる黄金時代を築き上げた。江戸時代中ごろには名古屋城の中で「御深井」(おふけ)と言われる灰釉の美しい陶器も焼かれ我が国を代表する産地となった。
現代になり洋食器も多産するようになり日本の和洋食器を作る最大の産地として君臨している。近くに瀬戸・赤津・品野の名産地がある。かつての桃山陶を作る窯と、量産型の大窯とが共存している。
22. 志戸呂焼(静岡県)Shitoro yaki
23. 瀬戸焼(愛知県)Seto yaki
日本の六古窯に一つで、平安時代に猿投地区で須恵器が作られたのが始まりとされている。やがて武家社会の中でも灰釉のかかったものを中心に、日常の雑器が大量に生産されるようになった。現代は日用の食器を型をつかって作る手法で大量に生産している。東日本を中心に「せともの」という言葉で陶磁器全般を言うことがあるが、これは如何に瀬戸焼が室町時代以降に一般化・大衆化したものであるかを表した言葉でもある。
瀬戸には赤津・品野などの名産地がある。
23. 常滑焼(愛知県)Tokoname yaki
平安時代に始まった常滑焼は当初経塚のような宗教儀式用具などを作っていたが、鎌倉時代に入り大量の甕・鉢・壺を作るようになった。中世の常滑焼の窯数は千を超えていたと思われる。その多くは穴窯で焼かれ大量生産を可能にしていた。その後現代になり、常滑は電柱の碍子(がいし)や土管を生産するようになりかつての産地の面影はすっかり消えてしまった。そんな中現在は若手の製作者(作家や職人)たちが新しい制作活動を始めている。急須(茶器)などの生活雑器や皿、茶碗などが現代の常滑の主な生産品であり、特に急須の質の高さが秀逸で人間国宝を輩出したことでも知られる。
24. 万古焼(三重県)Banko yaki
紫泥を使った急須で有名な万古焼は陶器と磁器のちょうど中間の炻器(せっき)と呼ばれるもので、三重県四日市を中心に作られている地場産業である。また土鍋の生産でも有名で海外にもその多くが輸出されている。
紫泥を使った急須は使い込むほど艶が出て味わいのあるものに変化していく。長年の間に手になじみ日常の道具として使い手のものになっていくのが万古焼の魅力の一つでもある。
24. 伊賀焼(三重県)Iga yaki
三重県伊賀市で焼かれる赤褐色に白い長石粒のある陶器である。その始まりは桃山時代に伊賀地方をおさめていた筒井定次によって窯が作られ、壺や甕のほかに、茶入れや水指、茶壺などが作られるようになったのが始めとされる。焼きしまった生地に自然釉(ビードロ釉)がかかり侘び寂びの中にも力強い武士の世界を感じさせるような器である。今では茶器よりも土瓶。土鍋、行平などが多く焼かれている。
筒井伊賀、遠州伊賀と呼ばれるかつて焼かれた伊賀焼はその数が少なく、大変貴重で今では見ることも難しくなっている。
25. 信楽焼(滋賀県)Shigaraki yaki
日本の六古窯の一つで信楽の独特な荒い粒の土を使った火に強い陶器である。赤みを帯びた緋色の焼肌といわゆるビードロ釉と呼ばれる自然釉がかかり、侘び寂びの世界を作っている。
室町時代あたりから常滑、越前と同様に雑器としての大壺や小壺を生産しており、当時は茶壺や水瓶、種壺に使われていた。その多くは今でも尚人気を集めている。現在では、様々な生活雑器のほかに陶板・タイル・植木鉢やタヌキ・フクロウの置物などを作っている。信楽は地理的にも伊賀と近く、昔は茶陶としてともに発展してきた産地であるが、今では伊賀に比べてはるかに大きな産地になっている。
26. 清水焼・京焼(京都府)Kiyomizu/Kyo yaki
江戸時代に尾形乾山(けんざん)、野々村仁清(にんせい)、青木木米(もくべい)などの数々の名工が生まれ、その技術の高さと雅な芸術性から日本を代表する焼き物になった。清水焼は約300の手作りの小さな窯を中心にこぢんまりとした産地を形成している。しかしその華やかさの陰で、多くの窯は現在、伝統産業を守るための後継者難に直面し、存続の危機に直面している。
かつて京焼は清水焼、粟田口焼、八坂焼、音羽焼、御菩薩(みぞろ)焼など市内各地にあった焼物の総称として使われていたが、現在は清水焼だけが残り清水焼が京焼と言われるようになっている。清水焼は茶器や和食の季節感を大切にする器として長い伝統と歴史の中で磨き抜かれてきたもので、その美しさは陶器の温かみや磁器の気品の中に良く表れている。ただし交趾釉(こうちゆう・鮮やかな黄・青・紫・緑色などの釉薬)や楽焼のものは酸や塩分によって変色することがあるので注意が必要。また京焼は様々な絵付けや焼き物の技法などで国内の他の産地に大きな影響を与えた。いわゆる京都の感性が手ずから感じられ、優美な世界が眼前に広がる焼き物である。
28. 出石焼(兵庫県)Izushi yaki
白磁をその軸とした兵庫県豊岡市出石町の磁器である。半乾きの生地に彫りを施し白磁として仕上げた浮彫、透かし彫りの技法は他産地ではあまり見られないものである。江戸時代に近くで白磁石の鉱脈が発見されてから飛躍的に発展した産地で伊万里から陶工を招いて赤絵や染付を始めたのが最初である。今でも他産地の上絵用の白磁器なども作っている。観光地出石を彩る焼き物として人気も高い。
28. 丹波立杭焼(兵庫県)Tanbatachikui yaki
登り窯を使って4・5日間も松を使って焼き続けるため、窯の中で松灰が降りかかり「灰被り」と呼ばれる独特の自然釉の模様が器面にできる。炎のあたり方や粘土に含まれる鉄分とが反応し赤褐色の濃いいろが出ると赤土部窯変、このように様々な色合いの景色が生まれる。
その歴史は11世紀ころまでさかのぼり、壺・甕・すり鉢を作っていたが、やがて江戸時代後半から茶器も作られるようになり多くの名品を生んだ。「傘徳利」に見られるユニークな形、流し釉の大甕は先人のセンスが感じられ必見である。
29. 赤膚焼(奈良県)Akahada yaki
赤膚焼は桃山時代に奈良県五条に豊臣秀長が窯を作らせて陶器を焼かせたのが始まりと言われている。小堀遠州の選んだ、遠州七窯の一つで、赤膚の名の通り赤い肌の生地に釉薬をかけると、ほんのりとしたピンク色の器になることが多く、この上に奈良絵と呼ばれる御伽草子の世界を可愛らしい絵にした器は今も人気がある。ただ赤膚の土は焼き上がりが難しく窯出しの際の成功率が低いと言われている。
31. 牛ノ戸焼(鳥取県)Ushinoto yaki
32. 出西焼(島根県)Shussai yaki
32. 温泉津焼(島根県)Yunotsu yaki
33. 備前焼(岡山県)Bizen yaki
釉薬を使わず硬く焼き締められた陶器で様々な窯変(窯の中で人為的でない偶然の模様や色や肌合いができること)が出ることで知られている。
日本の六古窯の一つで、その歴史は平安時代の須恵器にさかのぼる。田上(ひよせ)と呼ばれる粘土で焼かれた茶褐色の器肌は鉄分を多く含むもので、先祖代々大切に貯蔵されたブレンド土を使用するため、窯によって焼き上がりに違いがあるのも備前焼の面白さと言える。桃山時代には茶陶として発展したが、その後は大量生産の雑器に押されて衰退した時期もあったが、作家の手を離れ焼成、理想とするその焼けを追い求めまたその焼けで価格も違えてくる、およそマニアックで楽しい世界観は独自のものであり他の焼き物には無い魅力でもある。
35. 萩焼(山口県)Hagi yaki
茶器を中心に焼いてきた産地が山口県の萩で、昔から茶道を楽しむ人々に人気の陶器である。萩焼は朝鮮半島の高麗茶碗に似ており、釉薬がひび割れのような貫入を作り、所謂使い込んでいくと様々な器肌をつくる「萩の七変化」で有名である。
使い始めは茶漏れが起きることが多いが使い込むうちにこれもなくなり、味のある器になっていく。昔から「一楽、二萩、三唐津」と言われて茶道を中心として評価の高い陶器として多くのファンを獲得してきた。萩の町は町全体が公園のような自然の美しさに囲まれた風光明媚な所である。山有り川有り海有り、明治維新の歴史あり、美味しい魚有り。是非一度は訪れてみてほしい町である。
36. 大谷焼(徳島県)Otani yaki
四国巡拝に来た薩摩国がきっかけで十三代蜂須賀公より藩窯としての初窯(1781年)が始まりと云う焼き物。もともと大谷は染付磁器の産地であったが、時代の流れの中でその窯はすっかり姿を消してしまった。そこに徳島の藍染で使う大甕の需要ができて、大谷焼はこの大甕を中心に産地としての息を吹き返すことになった。水琴窟(すいきんくつ)用の大甕や生活雑器を主に様々な焼物を生産しており、砥部焼と並んで四国を代表する産地になった。
38. 砥部焼(愛媛県)Tobe yaki
江戸時代中期にはじめられた磁器。奈良時代から高名であった伊代砥の砥石を切りだす際にでる石屑処理に悩まされていた当時の人々に大阪の砥石問屋が知恵を貸し、磁器生産が始まった。幾度となく釉薬原料など試行錯誤に悩まされ、肥前からも技術を学んだ。原則的にはすべて手作りの器で大量生産はしなかったため独特の味わいがある磁器である。明治には伊予ボールの名で輸出されるなどその地位を確立。
高台の大きな「くらわんか茶碗」は、揺れる船の上でも飲食ができるようにと江戸時代に作られたもので、今でも大変人気の器となっている。
砥部焼の特徴の一つは、茶碗にしても皿にしてもやや厚手の磁器であることから、割れにくく丈夫な事である。その為実用として家庭の主婦好みの人気が高い器の一つである。
40. 高取焼(福岡県)Takatori yaki
秀吉の朝鮮出兵の際、黒田長政が朝鮮の陶工八山を連れ帰って窯を開かせたのが始まりと言われている。江戸時代には黒田藩の御用窯として盛んに陶器が作られていた。小堀遠州の遠州七窯の一つとして茶器を中心に多くの茶碗・皿・水指などが作られた。
きれい寂びと言われるきちんとした「造形」の、遠州好みの瀟洒な器で、今でも多くの人に人気を得ている。
古高取と呼ばれる陶器はこれとは対照的に織部風の大胆な意匠で芸術性も高かったが廃窯になってしまい、現在はきれい寂びの「高取焼」が代々続くその暖簾を守っている。
40. 小石原焼(福岡県)Koisiwara yaki
福岡県朝倉郡東峰村で焼かれる。高取焼の窯元と目と鼻の先に位置しながらも独自に発展を遂げ、江戸時代の黒田藩の影響で盛んに陶器が作られていた。この地域でも小鹿田焼と同様飛びかんななや刷毛目、櫛描き、指描き、流し掛け、打ち掛け技術が伝わっている。のちに小鹿田村に小石原の陶工である柳瀬氏がこの技法を伝えた事が兄弟窯と言われる所以である。2017年には人間国宝の指定を受ける名工も輩出され、現在50軒近い窯元達が新たな作風も取り入れながら伝統と革新の小石原焼となっている。
41. 有田焼・伊万里・鍋島焼(佐賀県)Arita/Imari/Nabeshima yaki
有田町で焼かれる磁器は天草陶石を使った高品質なもので輸出用として近隣の伊万里港からヨーロッパにも輸出されていた。そのため伊万里焼ともいわれ17世紀~18世紀にかけてオランダの東インド会社を通して多くの磁器が輸出された。初期伊万里、古九谷様式、柿右衛門様式、鍋島様式などがあり、中でも鍋島藩の藩窯でやかれた高級磁器である鍋島焼は我が国の技術の高さを誇るものとなった(御庭焼)。当時藩窯の職人たちを、関所を設けて窯のある大川内山から逃げないようにして、技術の漏れを防いだほどであった。今でも生涯を賭けたこの職人たちの墓石が大河内山に見える。
有田焼のほかにも三川内焼、波佐見焼なども伊万里港から積み出されたため、これらを総称して伊万里焼とも云う。
有田焼は秀吉の朝鮮出兵の際日本に連れてこられた陶工たちの一人・李三平が有田町の泉山で原料になる陶石を見つけたことに始まる。毎年ゴールデンウイークに開催される有田陶器まつりは陶器好きの多くの人々が全国から集まり大変賑わう。
41. 唐津焼(佐賀県)Karatsu yaki
唐津焼はかつては佐賀県有田地方から長崎県北部佐世保・平戸地方に至る広範囲の焼き物を指しての名称であったが、ここでは朝鮮半島から伝わってきた唐津地方を中心に焼かれている陶器の説明をば。
桃山時代になって朝鮮半島の焼き物の血統を引く唐津焼が注目されるようになり、素朴さと侘びの世界を感じさせる茶碗が茶の湯とともに人気を博した。西日本では「からつもの」と言えば、東日本の「せともの」と同様に焼物全般のことを指すまでに至った。
唐津焼の特徴は、朝鮮半島の焼き物の技術がそのまま伝わり、しかも現代に残っている点である。特に、蹴轆轤(けろくろ)や叩き作りと言った技法は唐津独自のものとして今も伝わっている。絵唐津・朝鮮唐津・斑唐津(まだらからつ)・三島唐津・奧高麗・粉引唐津など様々な様式があり器好きを楽しませてくれる焼き物である。
42. 三川内焼(長崎県)Mikawachi yaki
平戸焼とも呼ばれるこの焼き物は、九州の他の産地がそうであったように秀吉の朝鮮出兵の際に連れてこられた陶工によって作られたのが始めである。白磁に染付を乗せた三川内焼は、天草陶石を使って作られている。主な技法としては、超絶技巧とされる透かし彫りがあり、涼しげで美しい器となっている。また唐子の絵が特徴的で、皇族や将軍家で使うものには7人、大名が使うものには5人、一般庶民が使う器には3人と定められていた。もう一つの特徴は非常に薄手であることで(白胎)その技術の高さは現在にも伝えられている。
42. 波佐見焼(長崎県)Hasami yaki
江戸時代から一般庶民向けの磁器を生産してきた産地で、船の上に置いて使う「くらわんか茶碗」や最近では波佐見地方の「割れにくい」という方言からくる「ワレニッカ食器」で知られた産地である。
ここの技術は朝鮮出兵の際、朝鮮の陶工・李祐慶によって時の大村藩にもたらされたものである。またコンプラ瓶と呼ばれる江戸時代の醤油や酒を入れる有名な輸出用瓶は波佐見を代表するもので、骨董愛好家の人気の焼き物のひとつとなっている。
現在でも使いやすい器の産地として波佐見は知られており、その熱心な研究姿勢から業界でも大きな勢力を持ち多岐にわたる販路へ多くの食器が作られている。
43. 小代焼(熊本県)Shoudai yaki
44. 小鹿田焼(大分県)Onta yaki
「飛びかんな」の技法で有名な焼物である小鹿田焼は、その技法が代々家族にのみ伝承されてきたため、昔ながらの伝統的技法が今も残っており国の無形文化財として登録されている。
大分県日田市皿山には粘土を砕くための水車などが今も残り、独特の景観と文化的風情を楽しむことができる。「飛びかんな」の技法はかつての中国にもあり、何らかの形で伝来したものと思われる。これは轆轤(ろくろ)を回しながらへらやかんなで半乾きの生地にとびとびの縞模様をつけるもので、信楽などでも似たような技法は見ることができる。山を隔てた隣の谷で焼かれている小石原焼とは兄弟関係でその歴史や技法に似たものがある。
46. 薩摩焼(鹿児島県)Satsuma yaki
薩摩焼は大きく2つあり、いわゆる白薩摩と呼ばれる華やかで豪華なもの。もう一つは黒薩摩と呼ばれる一般大衆向けの雑器とに分けられる。薩摩焼の陶工は秀吉の朝鮮出兵の際に朝鮮から渡来し、島津藩の保護のもとで発展してきた。白薩摩は金襴錦手の華やかさが海外で評判となり、幕末から明治にかけての薩摩藩の主要な輸出品となっていた。一方黒薩摩は鉄分の多い土を使う重量感のあるものとなっている。「ヂヨカ」と呼ばれる薩摩の焼酎用の酒器は有名。幕末から明治にかけて京都や横浜などでもこの薩摩焼が作られ、その多くは海外に輸出されていった。この薩摩焼は京薩摩・横浜薩摩と呼ばれていた。
47. 壺屋焼(沖縄県)Tsuboya yaki
大胆で伸びやかな絵付けで知られる壺屋焼きが今日あるのは 民芸運動家らによるところが大きい。彼らは日本国内で生産される日用雑器の「用の美」と呼ばれる実用性と芸術性に光を照らした。そして壺屋焼の鮮やかな彩色に目を向け、庶民の日用品でこれほどまでに装飾性を兼ね揃えたものは珍しいと評価している。その歴史は古く平安時代から鎌倉時代までさかのぼるという説もある。太平洋戦争で各地が焦土と化す中、壺屋は比較的軽微な被害で済んだが、一帯の都市化の進行とともに薪窯の使用が規制されると、存続の危機を迎えた。そのため、今日では薪窯を認可した読谷を始め、壺屋地区以外にも窯元が分散することとなり、およそ100軒ほどの窯元が県内に見られる。

